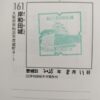■城名
山口城(やまぐちじょう)
■別名
山口屋形、山口御屋形、山口政庁
■所在地
山口県山口市滝町1-1
■見ごたえ
★★
■築城年
元治元年(1864)
■廃城年
明治6年(1873)
■築城者
毛利敬親
■主な城主
毛利氏
■天守
なし
■城分類
平城
■遺構
曲輪、石垣、横堀(水堀)、門
■指定文化財
国史跡
■歴史(ChatGPTより)
山口城(やまぐちじょう)は、山口県山口市の中心部にあった城郭で、近世に毛利氏が築いた居館・政庁の役割を担った城である。江戸時代初期に築かれたこの城は、毛利氏の藩政の一部を支えた拠点として重要な役割を果たし、現在は「山口城跡」として国の史跡に指定されている。
山口城が築かれる以前、この地域は戦国時代に大内氏が本拠を置いたことで栄えた。大内氏は山口に壮大な館を構え、京文化を取り入れた国際都市を形成したが、16世紀半ばの大寧寺の変によって滅亡した。その後は毛利氏の支配下に入り、江戸時代を迎えると萩城を本拠とする長州藩の領域の一部となった。
山口城の築城は、萩城の支城として毛利氏の支配体制を補完するために始まった。築城の中心となったのは、毛利輝元の子で藩主となった毛利秀就の時代である。萩城が本拠であったものの、藩の政治や文化の中心を補佐する城として山口の地が再び注目された。特に、交通の要衝である山陽道に近いこと、かつて大内氏が治めた政治的・文化的基盤を活用できることから、山口に城を置くことは戦略的に重要であった。
山口城は平城であり、石垣や堀を備えた城郭であったが、萩城のような大規模な天守は築かれなかった。藩の政治的拠点としての性格が強く、政庁や御殿が城の中心に置かれたことが特徴である。周囲には水堀が巡らされ、防御とともに威容を示した。こうした姿は、江戸時代の諸藩が本城のほかに別の居館を置いて支配体制を強化する在り方の一例といえる。
江戸時代後期になると、山口城は特に重要性を増していく。萩城は藩都であり続けたが、交通や経済の便に優れる山口に政庁を置く動きが強まったのである。幕末には長州藩の政治・軍事活動の拠点としても利用され、明治維新の胎動に深く関わる舞台となった。吉田松陰や高杉晋作ら、維新の志士たちも山口の地で活動しており、山口城は近代日本の出発点と密接に結びついた存在であった。
明治維新後、廃藩置県によって長州藩は山口県となり、山口城は県庁舎として用いられた。しかし時代の変化とともに城の施設は取り壊され、多くの建物が失われた。堀の一部や石垣が往時を伝えるにとどまったが、遺構は大切に保存され、城跡は山口市の歴史的景観の一部として残されている。
今日の山口城跡は、毛利氏の歴史や幕末維新の舞台を伝える貴重な文化財として評価されている。堀や石垣に囲まれた敷地には、かつての政庁や御殿が存在したことが確認されており、発掘調査によって詳細な構造が明らかになりつつある。また、周辺には大内文化を今に伝える遺跡群や、毛利氏庭園、志都岐山神社などの史跡も点在し、山口の歴史的景観を形作っている。
山口城は、戦国時代の大内氏館と、江戸時代の毛利氏政庁とを結ぶ歴史の架け橋である。華やかな天守を誇った城ではないが、文化と政治の中心として地域を支え、日本史に大きな影響を与えた。現在も残る遺構に触れることで、長州藩の歩みや幕末維新の激動を実感できるのである。
■場所
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■城巡り記録
2025年8月9日

幕末の激動の時代、毛利家藩主毛利敬親が萩から山口に拠点を変更するために築いたお城です。

山陽道が通る交通の要所として山口の方が向いていたのだとか。

行ってみると立派な門が現存していました。

これはすごい大きさの門ですね。
門をくぐると何があるのか期待したのですが、そこは広場になっているだけで何もなかったです。

![]()
にほんブログ村
![]()
にほんブログ村
![]()
にほんブログ村
![]()
にほんブログ村

人気ブログランキング

お城巡りランキング

お城・史跡ランキング