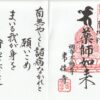■城名
高山城(たかやまじょう)
■別名
天神山城、臥牛山城、白雲山城、青山城
■所在地
岐阜県高山市空町
■見ごたえ
★★★
■築城年
天正16年(1588)[高山城]、元禄5年(1692)[高山陣屋]
■廃城年
元禄8年(1695)
■築城者
金森長近[高山城]、伊奈忠篤[高山陣屋]
■主な城主
金森氏、前田氏[高山城]、伊奈氏[高山陣屋]
■天守構造
望楼型[2重3階/1600年頃築/破却]
■城分類
平山城
■遺構
曲輪、石垣、土塁、横堀
■指定文化財
県史跡(高山城跡)、国史跡(高山陣屋跡)
■歴史
高山城の築城者は金森長近(かなもり ながちか)です。長近は元は織田信長に仕えていましたが、本能寺の変後に豊臣秀吉に従うようになり、数々の戦功を上げます。その功により、1585年(天正13年)に飛騨国の領主に封じられ、最初に松倉城に入城しました。
しかし、行政運用上の理由もあって城下町の整理に着手。1590年代後半に城を築くべく城山に城郭を築き、城下町もあらたに整理しました。これが後世「古い町並み」として保存された城下町です。
城は、約687メートルの城山上に築かれていました。城内には天守、御殿、櫓、門、空堀も設け、城主の行政運用の中心にしました。周辺には家臣の屋敷も配置して城下町との結びつきを強化しました。城下町の道路も整理して格子状にするという近世城下町のモデルに近く、行政上も文化上もよく設計されたものです。
金森長近は秀吉のもと茶道に秀でた文化人としても活躍しました。その影響もあって城下町には茶道文化も根付き、後世「茶の湯文化の地」としても広く認識されたという歴史があります。
金森氏の治世は約100年以上続きます。その後、1695年(元禄8年)に金森氏が転封になると城も行政上の地位も揺らぎ、最終的に大野藩が入封しました。大野藩は城を再建せず、城の建物も撤去して整理しました。
城は近世後期に完全に廃城となりますが、城下町に根ざした文化は消えてはいきません。行政運用こそ町方に委ねられても、町の文化、伝統、町並みというかたちに後世に継承されたのです。
現在、城跡は城山公園という緑地に整備して解放しており、地元の人の憩いの場となっています。展望台も設置され、ここから望む高山市の町並みもまた格別です。春には桜、秋には紅葉に彩られ、城跡周辺の緑も季節によって表情を変えています。
また、城下町には「古い町並み」とよばれてきた町屋、寺院、史跡が数多く保存してあり、城の歴史もあって「小京都」と評して愛され続けています。城という「権威」と「行政」の中心地という視覚的象徴に加え、文化という「心のよりどころ」として後世に生き続けているという点にこそ、高山城の真価があるというべきです。
戦国時代から近世にかけて、この地に確かな足跡を刻み込み、後世に文化という遺産を残しました。
■場所
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■城巡り記録
2025年6月7日


高山の観光地である陣屋の方はたくさんの人がいますが、こちらの高山城までくる人は少ないと思います。

登ってみると結構な山。


土曜日で外国人観光客もたくさんいて、古い町並みの方はものすごい人なのですけど、こちらは閑散としています。








高山城も良いところですよ。
![]()
にほんブログ村
![]()
にほんブログ村
![]()
にほんブログ村
![]()
にほんブログ村

人気ブログランキング

お城巡りランキング

お城・史跡ランキング